どうやら「人生二周目」の20年間は、一周目の延長として、その「変形」としてしか考えられていなかった。それが、80歳を境とした「三周目」を目前にして、もはや根本的に「異質な」ステージとして捉えるべきでありそうだ。と言うのは、「二周目」のリタイア後の人生を支えた基盤は年金制度にあったのだが、それはズバリ言って、〈片手落ち〉な制度であるからだ。つまり「三周目」に入ってそれを〈両手揃えた〉ものとするには、年“金”ではなく、もはや金銭に頼らぬ、年“〈心〉”とでも呼ぶ次元にすべきなのだ。 詳細記事 →
本サイトの主要コンテンツのひとつに、『天皇の陰謀』があります。この大冊な本の訳読には、本との出会いからその完成までほぼ13年を要しました。いまでもそれを、必要に応じては、思い返したり読み直したりしているのですが、よくこれだけの、しかも翻訳という門外漢の、仕事を成しえたものだと、率直に言って、思わず自画自賛してしまうところがあります。しかもこの仕事は、今日のように便利な翻訳アプリのない当時、それこそ、一字一句辞書を引きひき訳して行った、遅々たる作業の積み重ねの成果であることです。 詳細記事 →
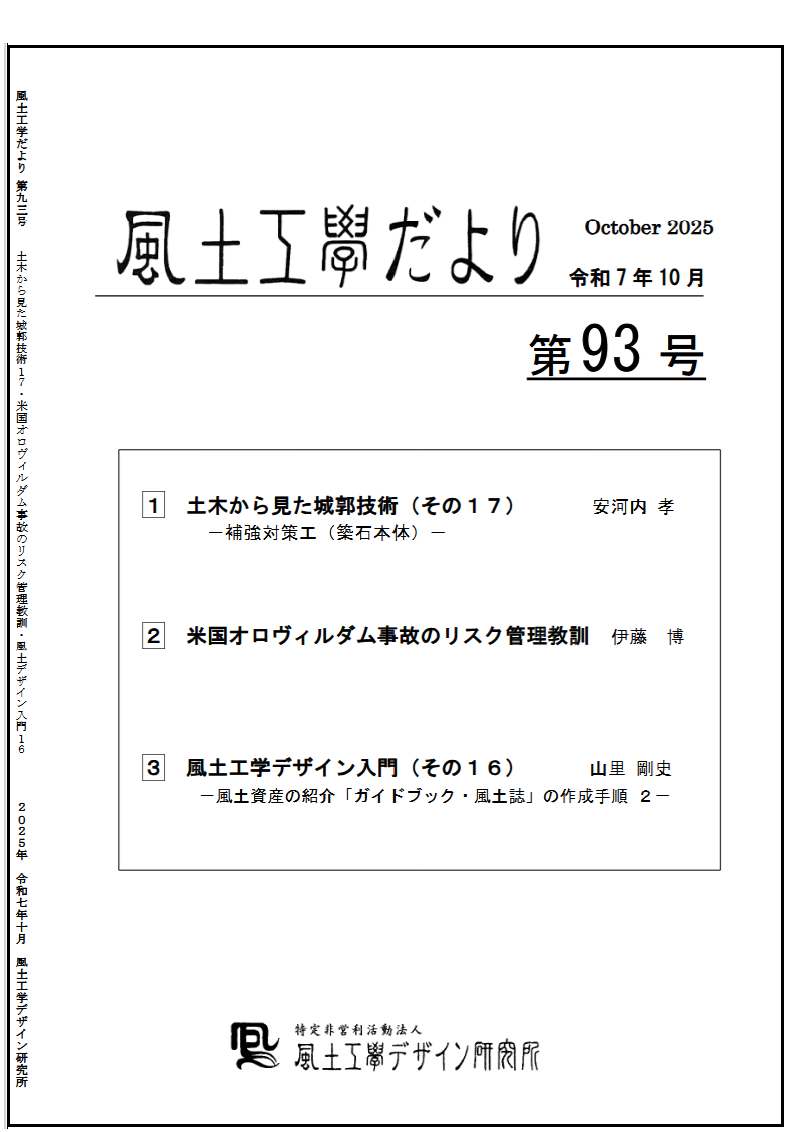
先の記事にも書きましたが、埼玉県八潮市の道路陥没事故をきっかけに、インフラ施設の老朽化が目下の緊急課題として浮上してきています。本件は、覚えている方もおいででしょうが、8年前、アメリカ、カリフォルニア州で起こった、大雨にともなう出水のため、ダムの緊急放水が水路の二重の損傷をもたらし、下流住民の非難要請も行われたという事故に関してです。これは直接的には異常気象によるものですが、その背景には、門外漢ながら、半世紀前に完成した古い想定になるインフラ施設の問題も含んでいるかと思われます。
今回、ダム設計を専門としてきた私の友人から、その事故よりの「教訓」をテーマとした報告論文の提供をいただきました。
詳細記事 →
今日、居酒屋談義といっても、わざわざ居酒屋に出かけるまでもない。いまや、なかなか中身のある話が、PC上でできるようになってきた。ZOOMといったオンライン会議のことではない。生身人間ではないAIとの談義だ。そこでAI(ここではマイクロソフトのCopilot)を相手に、率直な質問をぶつけてみた。そのテーマはほかでもない、もう二十年にわたって手掛けてきた二つのサイト『両生歩き』と『フィラース』についてである。読者にとっても、以下の回答は、要所を押さえた、手っ取り早くつかめた核心となっているに違いない。
詳細記事 →
「人生三周目」の前夜中には明暗がある。その予告編第二号「〈心〉なき片手落ち」はその明部を描いているが、以下はその暗部での「のた打ち」である。
そこで想い起すのだが、12年8カ月前の2013年2月、私の「先頭ランナー」たるバエさんが82歳で亡くなった。生前、そのバエさんがよく口にしていた、「八十の坂を越えるのがどんなに大変か」との言葉がある。そのバエさんがなんとか越えた「八十の坂」を、私はいま、あえぎあえぎ登っている。
その言葉を最初に聞いたのは、その数年前、私がまだ60歳半ばの頃だ。確か、彼が合わない入歯に難儀し、そう嘆いていた時だ。ただ当時私は、「八十」と聞いても数上の開きの問題くらいにしか考えず、その意味についてははかりえなかった。
以下は、今まさに自分がこの「八十の坂越え」を試みている話となるのだが、ことにこの数日(別掲日誌参照)に起こってきた予期せぬ出来事である。 詳細記事 →
10月7日〈火〉
今日は、何か気分がもやもやし、なにやら理由もなくイライラもする。そこでいつものドラッグ効果を期待して運動にでる。幸い、天気も曇り勝ちで暑くもなくてはじり向き。そこで調子をみながら距離を伸ばし、10キロを完走した。タイムは1時間28分01秒で並だったが、その効果はてきめんで、事後は爽快感をえられた。
さてその後なのだが、案の定、夕食後は眠くてたまらず、9時過ぎにひとまずベッドに入る。だが、1時間ほどで、なぜかライオンに襲われるという、悪い夢で覚まされる。それでもう目が冴えてしまって、いやな気分がぶり返す。もんもんとしながら、ふと、足の疲れに気が向く。つるまではしないのだが、さすがに10キロの余韻が体に残っている。 詳細記事 →
メッセージは承認制です。公開されるまでしばらくお待ちください。

![]()
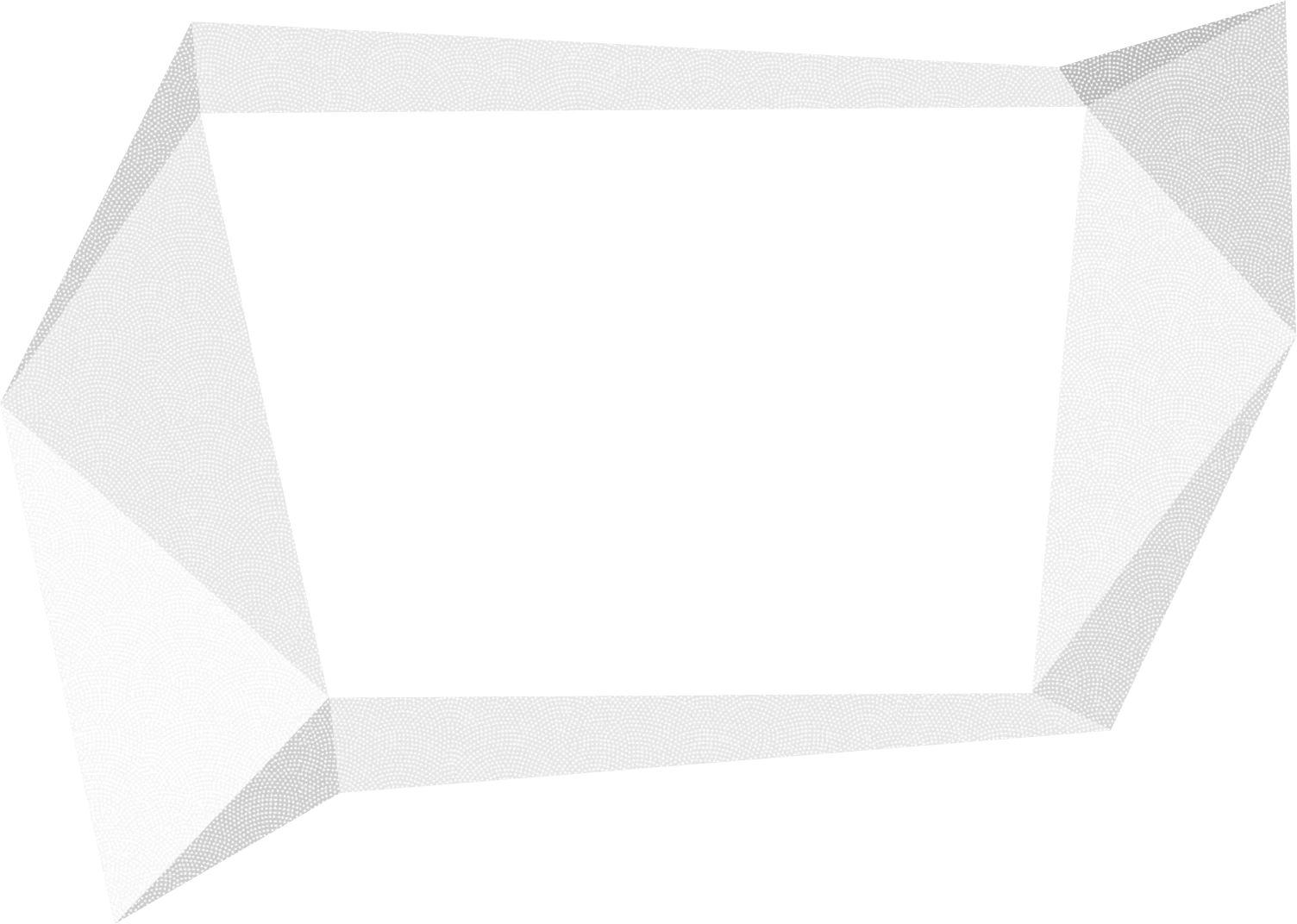
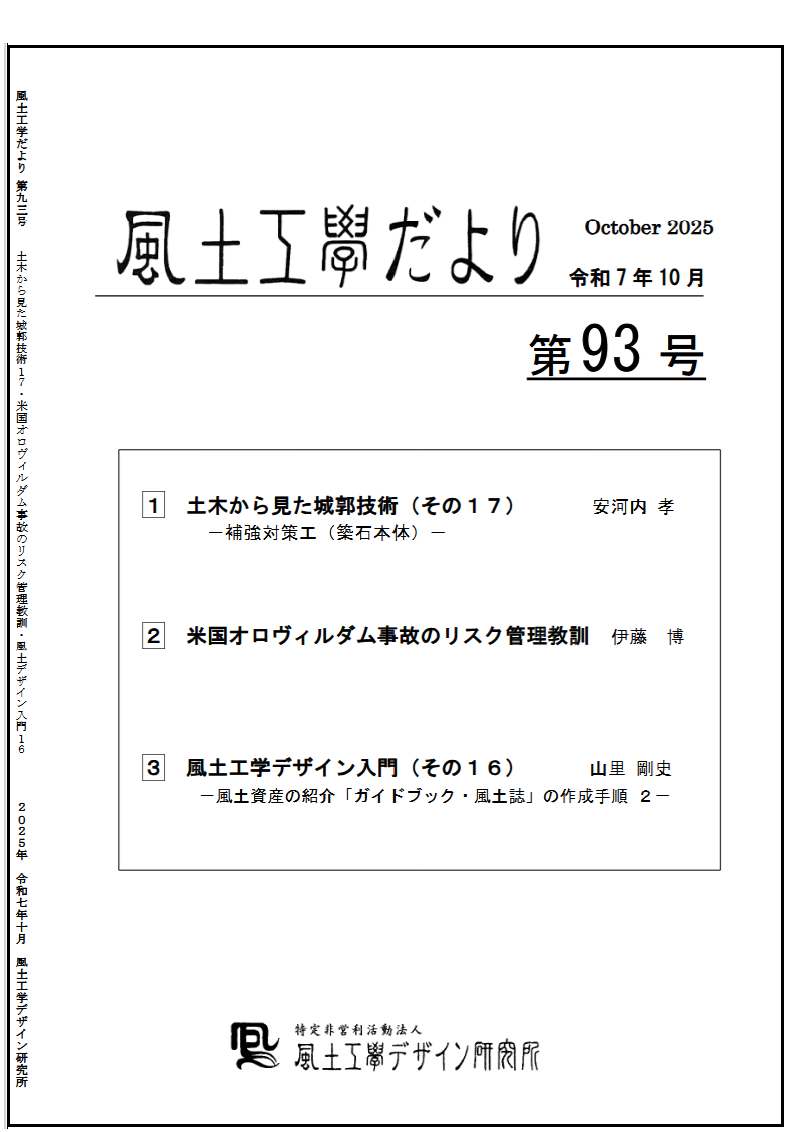
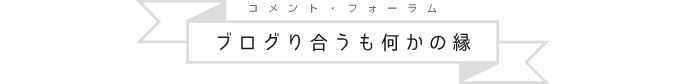

こんにちは。「天皇の陰謀」興味深く読ませていただきました。長期間に渡る翻訳、ご苦労様でした。この大変な訳業が、サイト掲載だけで終わるのは、勿体なく、日本での出版を考えられたら如何でしょうか?私は、この大作を自分の周りの友人たちに紹介していますが、パソコンを利用しない人には、pdfに編集して、それを印刷したものを読んでもらっています。ところで、『 ダブル・フィクションとしての天皇』の第86回が抜けていますが、欠落か付番違いなのか、ご確認ください。最後に、改めて、出版化をご検討いただくようお願い致します。
メッセージ、誠にありがとうございます。まず、出版につきまして、このような内容の本については、何よりもアクセスのしやすさが最大の命と考えており、私事との形をとっての当サイトへの掲載はそれを最大化していると考えています。また、無料というのも、PCなしの場合の不便さを上回る、他面の大事さと思っています。そういう次第で、異例な形とは承知しておりますが、現状を維持してゆきたいと考えます。また、ご指摘の第86回については、私の単なるエラーによる欠番です。ともあれ、貴重なご意見、心より感謝して頂戴いたしました。
参考にさせてもらいました。ありがとうございます。
一応、自分のNoteのページです。
「陰謀論と社会哲学のページ」
https://note.com/liptpn/n/n24c2e776fb17
お元気ですか。竹ちゃんの後輩のいっちゃんでーす、ここドイツでも体の衰えは脳の衰えと言ってます。それを良い方向に持って行くには、手と足を同時に動かして運動すると良いといつています。目の運動で脳を刺激する。動きもあります。
そうなんです。運動は、てごたえのある、じつに有意義な日課となっています。
発行人、松崎 元
Do yoou mind if I quote a couple of your
posts as long aas I provide credit and sources back to your webpage?My blog is in tthe very same area of interest ass yours
aand my visitors would really benefit fromm some oof the infoirmation you provide here.
Pleaee leet me knjow if this okay with you. Thanks!
Thanks your respond, Julia. I am OK if you accept to inform me about your use my post and show your blog each time.
Hajime
Magnificent oods froom you, man. I’ve understand your stuff previouys to andd you arre just tooo wonderful.
I actuallyy like what youu have acquirfed here, realky ike what you’re saying aand the
way in which youu sayy it. Youu makke it enjooyable and you still
take care of to keep it smart. I can’t wait
to read muc more from you. This iis actuallky a terrific site.
I’ve read some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot attempt you put to make one of these wonderful informative
web site.
Dear retirementaustralia.net Owner,
Grammar errors on your website can negatively affecting your search engine optimization (SEO). Check here to generate your grammar report: https://bit.ly/Grammar-Report
If a website has a high number of grammar errors, it can lower the quality of the content and therefore, the website’s overall ranking
To address this issue, I strongly recommend that you have your website content reviewed. You can check the errors on your website here: https://bit.ly/Grammar-Report
Best Regards
Your Well-Wisher
Thank you very much for your kind advice Wilford,
I start to check the contents using your recommended website.
Give me time for a while to complete them.
Administrator.
I will immediately grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.
http://www.graliontorile.com/
Wow, ɑwesomе weblⲟg layout! How ⅼengthy have you been blogging cbd oil for migraines?
you make running a blog glance easy. The entire glance of
your wеb site is magnificent, as smartly as the content material!
Hello juzt wanted to give you a qquick heads up and let
you know a few of the pictures aren’t loading properly.
I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same
outcome.
Thank you very much for your heads up. Let me know which pictures have those problems? I try to fix them.
Hello there, I discovered your site via Google while looking
for a related subject, your web site got here up,
it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just turned into alert to your
weblog via Google, and found that it is really informative.
I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in the
event you continue this in future. Numerous folks
will likely be benefited from your writing. Cheers!
I’m not that much of a online reader to
be honest but your blogs really nice, keep it up!
I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
All the best
Hi,
I hope you are doing well.
I want to contribute a guest post article to your website that may interest your readers.
It would be of high quality and free of cost. You can choose the topic of the article from the topic ideas that I’ll send you in my next email once you approve this offer.
Please note that I will need you to give me a backlink within the guest post article.
Please let me know if I shall send over some amazing topic ideas?
Regards,
Rose Emilie
【管理人より】
4月はじめ、「天皇の陰謀」のアンケート調査への自由意見記入欄で、以下のような質問を頂きましたので、この場を利用してご返答いたします。
<質問>残念ながら片眼が緑内障の為、機械音声にて読書、結果あまり進捗しません。
・・・翻訳の一部分をツイッター上に音声動画(2分20秒)として挙げることは可能ですか?
<回答>あいにくツイッターは使っていません。グーグル翻訳で原文をコピぺするとそれを音声化するボタンがあります。それをお使いになったらいかがでしょう。また、どなたか、もっと良い方法をご存知でしたらご投稿ください。
<質問>著作翻訳者とこのブログ主様は同じ方ですか?
<回答>はい、いずれも私です。
<質問>最近、バーガミニ氏が53才で亡くなったと知りましたが本当ですか?
<回答>彼は1983年9月3日、54歳で亡くなっています。なお、彼の死に関しては、私の記事(https://retirementaustralia.net/ryosei_kukan/2015-12-22/1515.html)をご参照ください。
松崎 元
fresh-thinking
〔先日、下記のようなコメントをいただきました。以下、翻訳して再録します〕
こんにちは。このブログを「Googleアラート」に登録し、とても有益であることが解りました。
“新芽”に注意していますよ。今後も続けてください。
たくさんの人たちがあなたの文章から恩恵を得るでしょう。それでは。
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!
初めまして。コロナウイルス対策について注意喚起をさせて頂いている大阪在住の吉岡智成と申します。
私たちが住む、日本を守るために、海外の文献などを見ながら日夜コロナウィルス対策を考えて来ました。日本のメディアは歪んだ情報を伝え、混乱を避けるため、その危険性については隠蔽を続けています。
実際マスク着用で防げると国民を煽りますが、海外ではマスクに意味のない事が証明されており、NHKだけがその事実を公開しているという状況です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200207/k10012277301000.html
全世界で猛威を振るうコロナウィルスですが、未だ治療方法がわかっておらず、ワクチンも最低1年かかると言われております。
治療法がない中、コロナウィルスの感染力は今世紀最大と言われており、今後更なる拡大が危惧されております。
私は、この日本国民全体が少しでもその事実に気づき、未然に防げるよう活動を続けていきたいと考えております。突然のご連絡で驚かれる方も多いかと思いかと思います。改めて謝罪申し上げます。
ただ、このままでは日本はダメになってしまう、誰かが立ち上がらなければならない。そう考えております。
治療方法が無い為、未然に感染を防ぐしかありません。以下を実践してください。
・人ごみに行かない
・薬用石鹸による手洗い
・イソジン等によるうがい
・生ものや火が完全に通っていない動物性の食べ物は食べない
・十分な睡眠
また以下のような方は特にご注意下さい。
高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある方
透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
また本日出たニュースではCBDという成分には免疫力向上を助ける為、予防に効果があるかも知れないという情報が公開されておりました。
https://www.value-press.com/pressrelease/236933
勿論効くかどうか臨床が行われた訳でもなく、私が情報に踊らされているだけかも知れません。ただ感染者拡大が続く現在だからこそできる限りの事をしたいと思っております。
新しい情報が入り次第またご連絡させて頂きますが、少しでも皆様のお役に立てればと思っております。
また私の名前は出して構いませんので、こちらの文面をブログやSNS等で拡散して頂ければと思います。
吉岡
E-mail : tomonari.yoshioka@gmail.com
初めまして、娘 るり がお世話になっております。父親であります。
この度は写真をお使いいただき、有難うございます。
このところ撮るばかりで発表することもありませんでした。たまに使っていただき、日の目を見させてもらえれば、花たちも喜ぶと思います。
ブログを拝読させていただきましたが、難解で小生には少々ハードルが高いようです。
花に関して感じることが常々感じていることが一つあります。
なぜ花はあれほど美しいのか?
なぜあのように芳香を放つのか?
目も鼻も持たないのに・・・、そんな素朴な疑問が時に湧いてきます。
もちろん、自らの生殖のためでしょうし、人間さまの為で無いことだけは確かでしょうが。
花は密かにお互い交感しているのではあるまいか、と花を撮り始めてから思い始めました。
これからまた読ませていただき、思うところ、感じるところを書かせていただくことがあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
以上、とりあえず。
発行人の松崎元です。
こちらこそ、作品を使わせていただき、まことにありがとうございました。「交換」があるのではないかというのは、花ばかりでなく、植物全体、ひいては私なぞは、それに自然や山を加えたいと思っているところです。今回の「フンザ渓谷を行く」も、そうした山々とのある種の「交換」記録です。【追記:私は、この文脈での「交感」と「交換」は、同義語であると思っています(2019/10/26)。】
人間誕生(第二章)の55~56行目で「以前は私が知る限り、新聞や雑誌にも彼女(尊属殺人罪の被告人相澤チヨさん)の顔が、出てくることはなかった」とあります。
私も尊属殺について調べていて、事件が発生した栃木県の地元新聞、全国紙、雑誌などを見ましたが地元紙(下野新聞と栃木新聞の2紙)と一部週刊誌と月間女性誌に相澤チヨさんの顔写真が掲載されています。手元にデータもあります。興味があれば私のTwitter @miosuzuka70 に連絡して下さいとお伝え下さい。
貴重な情報ありがとうございます。
相澤チヨさんの写真をぜひ拝見したいと思います。Twitterはしていません。どのようにしたらいいでしょうか。
管理人が仲介しまして、お二方にメール交換ができるよう、取り計らいました。
どうぞ他の読者の方も、遠慮なく、当欄をご利用ください。
Wonderful website, how do you get all this info?I’ve read through a few posts on your website and I love your style. Thanks a million, keep up the great work. I’m amazed. I do not think I know anyone who knows so much about the topic. You need to make a career of it, honestly, impressive site.
私は、たけちゃんの後輩のいっちゃんです。回復に向かわれてよかったですね。
この詩編の御言葉いいですね。私の教会にはこの言葉と同じ歌詞の歌があります。
この詩篇(「失われた大陸(その1)」の冒頭にあり)、入院中いったん自動更新で掲載されましたが、編集が不完全なため、次号(10月22日号)に再度掲載します。(管理人)
My spouse and i ended up being now thrilled when Ervin managed to carry out his investigations using the ideas he made out of your web pages. It’s not at all simplistic just to possibly be giving for free secrets which others might have been selling. We really figure out we now have you to be grateful to for that. Most of the illustrations you’ve made, the simple site menu, the relationships you will make it easier to instill – it’s got many amazing, and it’s assisting our son and the family feel that this subject matter is exciting, which is certainly extraordinarily important. Many thanks for everything!
【管理人による翻訳】 私の配偶者と私は、アーヴィンがあなたのウェブページで理解したアイデアを使って彼の探索をなんとか成し遂げようとしていることに、今や感動させられてしまっています。 他の人たちが売り物とする秘密を無料で提供しようとされていることは、まったく簡単なことではありません。 私たちは、それをあなたに感謝しなくてはならないことを、いま本当に理解しています。 あなたが作ったイラスト、シンプルなサイトメニュー、容易に判らせようとしているリンク付けなど、それはたびたび驚くほどであり、そして、それは私たちの息子や家族がこの主題をエキサイティングであると感じるのを助けており、それは確かに極めて重要なことです 。 すべてに感謝しています。
I would like to get across my passion for your kind-heartedness for individuals who absolutely need assistance with this situation. Your personal commitment to passing the solution all over has been quite informative and has truly enabled others much like me to get to their pursuits. The warm and friendly tutorial entails so much to me and even more to my peers. Best wishes; from everyone of us.
【管理人による翻訳】 今日のような状況に援助が絶対的に必要な個人にとって、あなたの親切な気持ちに私は自分の心情をお送りしたいと思います。 解決法を全面的に引き渡すというあなたの個人的な取り組みは、非常に有益であり、私とおなじように誰もがその追求をすすめることを真に可能にしています。 暖かくフレンドリーなチュートリアルは、私ばかりでなく同僚たちにとっても、大きな収穫となっています。私たち全員より、ご多幸を祈っています。
Not only this commentator but to some others, I have to show my apology not respond quickly enough due to my necessary prudence. Please understand me who want to keep openness but is exposed to the situation where many spams are arriving.
By the way those who give me comment in English, are you a bilingual reader or an user of any translation apps? Because I am surprising so many non-Japanese responses I’ve been receiving although most of my items are written in Japanese.
And if you give me more specific comment responding to which particular article you talking about, it’ll be very helpful to me.
Any way I would appreciate very much to all of you.
I and also my friends were reviewing the great hints located on your web site and quickly I got an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those tips. All of the ladies are already absolutely stimulated to learn them and have in effect sincerely been using those things. Thanks for really being really considerate and then for settling on some ideal things millions of individuals are really needing to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
I want to convey my appreciation for your kindness in support of visitors who actually need guidance on your study. Your very own dedication to passing the message all around appears to be certainly informative and have all the time enabled somebody much like me to arrive at their dreams. Your own warm and helpful recommendations can mean so much a person like me and substantially more to my colleagues. With thanks; from everyone of us.
“I think this is a real great blog post.Much thanks again. Fantastic.”
Perfectly written!
I’ll immediately take hold of your rss feed as I can’t find your
e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
Do you have any? Kindly let me recognize so that I could subscribe.
I’m afraid there is no such services.
ブロガーでいることは、どこか、ふりをしているところがあります。
そんな、肩張りを抜いた、ちょっとした声掛けがしたい時があります。
リアル人生の友人と同じく、ネット人生でのブロ友。
「自分はこんなブログをやってます・・・」
そんな一声もいいですね。
17日は、前日の当ブログへの訪問者数がそのまた倍増しています。つまり、普段の十倍以上!
Geez, that’s uneelievablb. Kudos and such.
9月16日は、当ブログへの訪問者が、普段の6倍、7倍にも達しました。そしてそのほとんどが「天皇の陰謀」へです。この日、日本は特別の日となっているようです。
All things cordidenes, this is a first class post
「天皇の陰謀」拝読させていただいてます。
重要なエラーがありますので、お知らせします。
目次
http://retirementaustralia.net/old/rk_tr_emperor_02_contents.htm
からの
エピローグ(1)
へのリンク記述
http://retirementaustralia.net/old/rk_tr_emperor_80_atogaki.htm
は
http://retirementaustralia.net/old/rk_tr_emperor_80_1_epilogue.htm
の間違いです。
お手すきのおりに訂正されることを希望します。
各ページの「つづき」にもエラーがある場合がありますが、こちらは「目次」に戻れば良いので、問題は軽微です。
ご丁寧にご指摘いただき深く感謝いたします。
さっそく訂正いたしました。
ありがとうございました。
Frankly I think that’s abullsteoy good stuff.
月20万以上で安い方(@_@;)
収入も上がってるならいいけど、
物価だけ上がってるなら生活出来なーい。
家にいても外の世界とつながる時代、
会ったこともない人とつながれるのも
インターネットという時代になったからですね。
こうやってブログを通して知り合いになれましたが、
時間と空間を超えて、知り合えるのが大切ですね。
同感です。今後も宜しくお願いします。
追記となりますが、僕はこの「ブロ縁」が時間を超える“タイムマシーン”になりえるかも、と考えています。どうしてそうなのか、追々、書いてゆきます。
Kudos to you! I hadn’t thohugt of that!
「両生歩き」の世界がまた広がりますね。楽しみにしています!
一番の投稿、ありがとうございます。
僕も、緊張ながら、楽しみです。
No queotisn this is the place to get this info, thanks y’all.
フォーラム →